HOME > 占領期を知るための名著 > 占領期を知るための名著 Vol.33 『占領下の言論弾圧』 松浦総三

GREAT BOOK占領期を知るための名著
- VOL.33
- 『占領下の言論弾圧』
松浦総三
ここでは、小説家・文芸評論家の野崎六助が
過去の名著から占領期の時代背景を考察します。
占領期を知るための名著シリーズ 第33回
contents
『占領下の言論弾圧』 松浦総三
本書の初版は、一九六九年に出た。
占領研究文献として最初期の収穫であるにとどまらず、占領期を生き抜いた気骨あるジャーナリストの体験ドキュメントとして、今も色褪せることのない貴重な書物だ。
テーマは一言に尽きる。占領軍権力は、いかに日本社会の言論を弾圧したか、である。著者は、徹底して現場証人として語り、その実相を暴いていく。言論弾圧といっても、けっして一元的なものではなく、そこには、現場に立ち会った者としてのさまざまな機微がはたらいている。著者が直接に接した検閲官にも多様な個性の人物がいた、という。
本書の色褪せない魅力は、「神は細部に宿る」の言葉のように、一行一行のディテールにある、といっても過言ではない。そして著者の立場は、明快なイデオロギーを発している。だが、事実を捻じ曲げた解釈は見つけられない。
イデオロギーといえば、後年、誰某(名は、とくに挙げない)が精力的に発信した「占領権力の言論弾圧によって日本人の創造精神は損なわれた」という説がある。歴史修正主義の露骨なデマゴギーの一例だが、その手口の事実歪曲ぶりは、すでに、本書のような誠実なドキュメントによって、原理的には論破されているはずだ。占領研究の場にも介入してくる「右翼偏向」の支離滅裂さを正すためにも、本書は有効なデータを提供するだろう。
本書の文体は激しく、人によっては、文学的な味わいや潤いのなさを感じるかもしれない。ただ《私の占領下の体験には、不思議と季節感がない》という、さりげない一行が印象的である。季節のない日々を疾走していったのだ、と納得させるものがある。
敗戦後、著者は、三一歳で、伝統ある総合雑誌『改造』の編集者となる。《新人なので、GHQの検閲課(CCD)に校正刷をもって事前検閲を受けに行く係をやらされた》。総合雑誌『改造』は、戦後民主主義のオピニオン・リーダーとなることを期待されたものの、数年後、無残な解体を遂げることになるが、その顛末を報告する章も、本書の後半の重要な項目である。
本書の基調は、軍国主義支配の戦中からGHQ支配の占領期に連続性をみる点で、一貫している。社会総体は歴史上未曾有の転換にさらされたとはいえ、言論統制という側面からみれば、そこにはゆるぎない弾圧システムが作動していた、ということだ。著者は、自分は一介のジャーナリストにすぎず、歴史家ではないと強調するが、その歴史意識は正当なものだ。
初版のあとがきには、こうある。
《占領時代は、まず日本共産党の解放軍規定ではじまり、それが一九五一年の日共新綱領で百八十度転換した。これが革新陣営にいる学者の、占領研究や評価をかなり混乱させる原因となった。そしてこの革新陣営の占領時代の評価は、一種の清算主義になってしまい、保守的な政治家やジャーナリストたちがいう「押しつけ憲法」や「日本を弱体化させるための改革」の裏返しに等しいものになった》
著者もまた、一時期、解放軍規定のトリコであったことを率直に認めている。そのうえで、著者は、占領期を三期に区分する。占領軍が解放的性格を保持していた初期、冷戦体制の進行とともに反動化していった中期、朝鮮戦争下の赤狩りの後期、である。
解放軍規定が幻想にみちた誤りであったことについては、再三、言及されている。著者の日本共産党との距離も、多くの左翼の例にもれず、次第に遠いものになっていく。
本書の主張のなかで最も重要なものは、GHQ方式の検閲(削除の痕跡を残さない指示)の発明者が日本の特高だった、という証明だ。多くの論者が、戦前の検閲システムは、伏せ字(××)や抹消(「……」などで、何字もしくは何行の削除と明らかにする)によるものだったが、占領期になると(削除箇所をつなげてしまうなど)検閲の跡を残さないやり方に変わった、それがアメリカ方式だった、という説を称えている。わたしも、平野謙や鶴見俊輔など経由ではあったと思うが、この説を疑うことがなかった。
松浦は、この説が《完全に事実に反してたてられたフィクション》だとして、厳しく批判する。著者の証明するところによれば、特高は、ある時期から徐々に、伏せ字も廃し、抹消の跡を残さない方式に切り替えていった。当時の総合雑誌のバックナンバーを調べてみた結果、《昭和一四年ごろには、ほとんど伏せ字がなくなっていることに気づいた》という。GHQ方式は、ただその「成果」を学び、引き継いだだけだ。占領軍がよりスマートな検閲法を初めて採用した事実はないのだ、と。
にもかかわらず、こうした「虚偽」の説が通用してしまった要因を、著者はいくつか挙げている。一つは、生命の危険すら脅かす検閲システムが、その実態を正確に解明する機会を奪ってしまったこと。一つは、私語や日記のレベルまで及んだ検閲の恐怖が占領下ではいちおう撤廃されたこと。などである。
要するに、戦前検閲体制は一種の「完全犯罪」をやってのけたわけで、その証拠をつきとめることは「不可能」ともいえる状況があった。著者が、この真実に肉薄しえたのは、彼の編集者・ジャーナリストとしての現場感覚がもたらせた「職人的想像力」だった、と思える。知性とは別物の動物的な嗅覚だ。
本書は、初版の数年後、一九七四年に「増補決定版」として再刊されている。その間、著者は大部の記録集『東京大空襲・戦災誌』の編纂に関わり、また、渡米し、アメリカの各地に散逸している占領関係資料の調査にあたった。プランゲ文庫(本書では、プレンジ文庫と表記されている)にも訪れている。
さらに、本書の主要な部分は、『松浦総三の仕事2 戦中・占領下のマスコミ』に、加筆・省略をほどこした上で再録されている。

『松浦総三の仕事2 戦中・占領下のマスコミ』
大月書店 1984.12
すでに、初版あとがきの段階で、占領時代の民族体験をなおざりにし、他人の国の出来事のように野次馬的にみるジャーナリズムの一般的風潮にたいする嘆きが発されていた。そして、その段階で右派による「歴史修正」もまた、台頭をはじめていたのだった。
いってみれば、松浦が慨嘆する情勢になればなるほど、彼の仕事の原理的な「正しさ」は輝きを増すのだろう。「正しさ」とは、彼がいっとき忠誠を誓った日本共産党の掲げる滑稽な「絶対無謬性」などとは異なる。それは、誤りに満ちた人間がぎりぎりに踏みとどまろうとするところに残される「愚かな」途の集跡だ。
本書の記述は、こうして、良くも悪くも、現場に徹した「低い目線」で支えられている。「目線の低さ」ゆえに、占領史全般を見渡すに足る視角には届かない。また、占領期の総合雑誌を中心にした思想史的目配りは書かれているが、現象的な事項の並列に終わっている。体験をともにした人びとを回顧し、彼らを描く《作家の才能が自分にも欲しいと思った》と思わず記すのは、歴史を書き残す手立てとして、いったんは小説形式を採用したいと願った、という意味なのだろうか。
さらには、竹前栄治と袖井林二郎の仕事にたいして敬意を表しながらも《GHQ史観に徹し、日本人不在の占領史》と断じている(『松浦総三の仕事2 戦中・占領下のマスコミ』の「はじめに」での記述)が、これは、いくら何でも舌足らずにすぎるようだ。
繰り返しいうが、松浦の営為は、歴史家の仕事とは別レベルにある。歴史観を対置することは的外れだし、己れの正当性を他者との差異化によって証明する必要が、彼にあるとも思えない。歴史家の仕事とは別レベルにあることによって、それぞれの価値が補い合う位置に達しているのである。
彼の占領史ドキュメントは、私的なものごとにこだわりながら、真逆に、そのことをとおして、公的な歴史からはこぼれ落ちてしまう「真実」に迫っている。読まれなければならないのは、まさに、そうした私的体験の指し示す「歴史」にほかならない。
何度でも、そのことを、確認しておこう。
- 『占領下の言論弾圧』
松浦総三 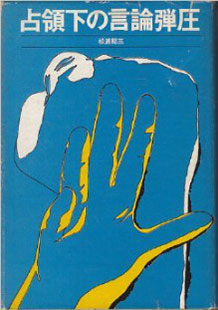
『占領下の言論弾圧』
現代ジャーナリズム出版会 1969
『占領下の言論弾圧 増補決定版』
現代ジャーナリズム出版会 1974.1

-
- プロフィール:野崎六助(のざき ろくすけ)
1947年 東京生まれ。
1960年から1978年 京都に在住。
1984年 『復員文学論』でデビュー。
1992年 『北米探偵小説論』で日本推理作家協会賞受賞。
1994年 『夕焼け探偵帖』で小説家デビュー。
1999年 小説『煉獄回廊』
2008年 『魂と罪責 ひとつの在日朝鮮人文学論』
2014年 電子書籍kidle版『李珍宇ノート』『大藪春彦伝説』『高村薫の世界』
http://www002.upp.so-net.ne.jp/nozaki
http://atb66.blog.so-net.ne.jp/ - プロフィール:野崎六助(のざき ろくすけ)
占領期を知るための名著 Vol.35 『拝啓マッカーサー元帥様 占領下の日本人の手紙』 袖井林二郎
Published on 2017/04/05 6:05
Category: 占領期を知るための名著
Tags: 拝啓マッカーサー元帥様 占領下の日本人の手紙, 袖井林二郎, 野崎六助
占領期を知るための名著 Vol.34 『マッカーサーの二千日』 袖井林二郎
Published on 2017/03/15 10:00
Category: 占領期を知るための名著
Tags: マッカーサーの二千日, 袖井林二郎, 野崎六助
占領期を知るための名著 Vol.32 『天皇と接吻 アメリカ占領下の日本映画検閲』 平野共余子
Published on 2017/02/15 10:00
Category: 占領期を知るための名著
Tags: 天皇と接吻 アメリカ占領下の日本映画検閲, 平野共余子, 野崎六助
占領期を知るための名著 Vol.31 『本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知っていること』『沖縄・米軍基地 観光ガイド』 須田慎太郎写真 矢部宏治文 書籍情報社
Published on 2017/02/01 10:00
Category: 占領期を知るための名著
Tags: 本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知っていることー沖縄・米軍基地 観光ガイド, 矢部宏治文, 野崎六助, 須田慎太郎
占領期を知るための名著 Vol.30 坂本義和/R・E・ウォード編『日本占領の研究』 袖井林二郎編『世界史のなかの日本占領』
Published on 2017/01/15 10:00
Category: 占領期を知るための名著
占領期を知るための名著 Vol.29 思想の科学研究会編『共同研究 日本占領軍 その光と影』
Published on 2017/01/01 10:00
Category: 占領期を知るための名著
Tags: 共同研究 日本占領軍 その光と影, 思想の科学研究会編, 野崎六助










