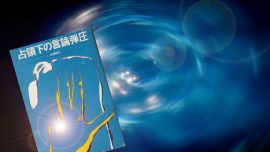HOME > 占領期を知るための名著 > 占領期を知るための名著 Vol.14 『イラク戦争のアメリカ』ジョージ・パッカー

GREAT
BOOK占領期を知るための名著
- VOL.14
- 『イラク戦争のアメリカ』
ジョージ・パッカー
ここでは、小説家・文芸評論家の野崎六助が
過去の名著から占領期の時代背景を考察します。
占領期を知るための名著シリーズ 第14回
contents
『イラク戦争のアメリカ』ジョージ・パッカー
イラク戦争の、主要な戦闘は、二〇〇三年の数カ月で終わった。その後の状況は、国家崩壊、占領、暴動から内戦、とさまざまに語られる。どう語られようと、共通するのは、事態は終結していないという認識だ。
本書は、その過程で成立した、アメリカ人ジャーナリストによる同時代の報告書である。その取材力、背景への幅広い目配りの点で卓越している。たんなる戦争批判の書ではない。むしろ、「開戦派」にまわった知識人としての、深い幻滅と自省と繰り言を多くふくんでいる。その意味では、善意の侵略占領者(いかにもアメリカ人らしいが、知性は不足していない)による、誠意にあふれた弁明の書というべきか。
ドキュメンタリー作品としての実質は豊かで多彩だ。占領下のイラク現地を駆け足でまわってレポートしたお手軽「ニュース本」の類いではない。
特異なイラク知識人との交友、討論をとおした彼の思想(思考遍歴)の紹介に始まり、戦闘が開始されてからは、たびたび現地に滞在し、戦争の「全体像」をできるかぎり「体験」し、報告していこうとする。イラク社会の「普通の市民」の生活と異見にページがさかれる一方、息子の戦死を哀しむ初老の(アメリカ小市民の平均像のような)父親の苦悩にも関心が向いていく。
あるいは、イラク取材時に協力を求めたボディガード数人に関するエピソードなどは、陽気な冒険小説のような興趣をそなえている。
戦争が傷つけた(もしくは、開示した)イラクとアメリカ社会の諸相が、貪欲に語られていく。
著者は、本書の前半で、戦争は不可避であったと論証していく。「どうしてサダム・フセイン(サッダームと表記される)のような独裁者を排除しないですますことができようか」。著者は、戦争を推進したネオコンの思想的源流が六〇年代の左翼に発している、と主張するのだが、この観点には、どうも納得がいかない。
従軍作家に準じるようなスタイルの部分は光るが、イデオロギー的系譜を正当化する記述には疑問が多く残る。
多彩で豊かではあるが、一個の「作品」としては感動を与えてくれない。
後記に、著者は書く。
《ここ数年間の出来事にもっともふさわしい反応は、正当化でも非難でもなく、イラク人とアメリカ人が同じように抱いた希望、払った犠牲に対する深い悲しみだとわたしは思うようになった。イラク戦争は議論の勝ち負けを争う対象ではない。悲劇そのものだ》
この悲劇感を共にできない。
身勝手そのものだ。
「アメリカ人が払った犠牲」? 「イラク人と同じように」?
全体を通読した後、著者の善意を疑うことはできないが、同じ理由で、その押しつけがましさへの嫌悪がつのる。これは、ジョン・ダワーの『敗北を抱きしめて』にたいしても共通する感情だ。
本書の結論めいた部分に、こうある。
《二一世紀はじめのアメリカは、イラクのような大きな難しい問題に取り組むには、政治的にあまりにも党派間の対立が激しく、力量が不足しているように思われた》
党派間のみならず、政権内部での個人的反目もふくめ、その政治的対立の根深さについての記述は、本書のいたるところに見つけられる。そのせいか、著者の立場は、親ネオコン、親ブッシュ・ギャングなのではないか、と思わせる部分も少なくない。しかし、そうであっても、「戦勝」後、長引く戦闘状態に直面したさい、政権中枢がとった、にわかには信じがたい道義的無責任と頽廃(こんな連中に「全世界の命運」を左右する巨大な権力が握られているのだ!)は、本書の記述からのみでも明らかに伝わってくる。
(アメリカの大統領にふさわしい人物は、今日、トム・クランシーの小説のなかにしか存在しないのか?)
わたしが本書に引きこまれた第一の理由は、本書の原タイトル『暗殺者の門』にあった。これの意味するところが、アメリカが開けてはならない「他国侵略のゲイト」をこじ開けてイラクに侵撃していったことの大胆な比喩ではないか、と直観したのだ。残念ながら、それを証明するページに読みあたることはなかった。
(独裁者が建造させた古代遺跡の俗悪なイミテーションを、戦争征服者のアメリカ人がジョークで「暗殺者の門」と名づけた、というのが真相らしい。アメリカが自らの傲慢な「暗殺者性」に気づいたのではなかった)。
別の意味で引きこまれたのは、従軍作家を理想とするふうな、その率直な語り口によってだった。
著者はまず、サミール・ハリールと名乗るカナン・マキアというイラク知識人を登場させる。《アラブ人でかつハヴェルやソルジェニーツィンのような反体制派》の亡命者。湾岸戦争時に、フセイン体制を弾劾する書物『恐怖の共和国』を刊行して知られるようになった。マキアとの交友がなかったら《わたしがイラクの未来に思いをはせることはなかっただろう》
しかし、著者の描くマキアの思想遍歴と肖像は、共感的なものではない。ともすれば、元左翼のネオコンの狂信者(と、著者に指弾される連中)と同列にあつかわれたりもする。人物観察は優れているのに、イデオロギー批判においては公平さに欠ける。
たとえば、著者は、グレアム・グリーンの『おとなしいアメリカ人』(半世紀ほど前の小説だが、イラク戦争の頃に映画化作品が公開された)を引き合いに出し、《グリーンは、アメリカが犯罪と失敗を犯す危険性は、その無知と独善に比例して高まることを一九五五年にすでに見抜いていた》と書く。これは、ネオコンの狂信者への批難するための権威づけだ。
その数ページ後には、第一次世界大戦時の反戦派ランドルフ・ボーンの一行が引用される。ボーンは「戦争は国家の健康法だ」と訴えたのだ。この引用は正当であるにもかかわらず、友人マキアを批判する文脈で使われているため、まったく的外れになっている(著者の眼には、マキアは文章家・イデオローグとしては卓抜だったが、政治家・論争家としては未熟だったと映る)。
むしろ、著者は、ボーンの「戦争と知識人」(一九一七年)から、次の一行を引き、なおかつ自分自身への反問として深めるべきではなかったのか。
《アメリカの知識人は現実に心をうばわれて、真の敵がドイツ帝国ではなくて、「戦争」であることを忘れているように思える》
ここでの「ドイツ帝国」をフセイン体制のイラクに置き換えるだけで、これは現在時の言葉になる。
本書の欲求は、イラク戦争の「全体像」を描くことにあったろう。イラクとアメリカ、その時代と社会の全体像に迫ろうとする多大な野心が、本書のいたるところにあふれている。あるいは、ボーンの同時代人ジョン・リードによるロシア革命の記録『世界を揺るがした十日間』が、著者の念頭にあったかもしれない。激動にさらされる事象を一瞬に捉えて「現代の古典」を産することを熱望したのかもしれない。
けれども、そうであるほど、本書は、不統一で雑然としたツギハギ細工のような読後感を残してしまう。これは、べつだん、著者の誠意や作家的力量がおよばなかったからではない。
本書の索漠とした質感は、ひとえに、帝国アメリカによる侵略の罪禍がもたらせた必然的な結実であるように思える。
『イラク戦争のアメリカ』ジョージ・パッカー 二〇〇五年
豊田英子訳 酒井啓子解説 みすず書房 2008年1月
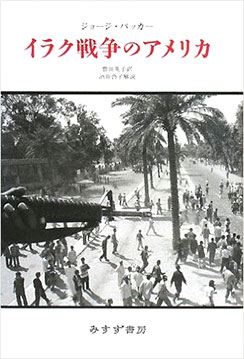
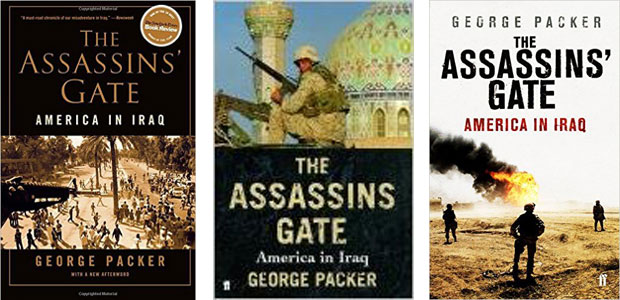
![Randolph S. Bourne [1886-1918]](/manage/wp-content/uploads/2016/05/img_nozaki_v14_01.jpg)
Randolph S. Bourne [1886-1918]

-
プロフィール:野崎六助(のざき ろくすけ)
1947年 東京生まれ。
1960年から1978年 京都に在住。
1984年 『復員文学論』でデビュー。
1992年 『北米探偵小説論』で日本推理作家協会賞受賞。
1994年 『夕焼け探偵帖』で小説家デビュー。
1999年 小説『煉獄回廊』
2008年 『魂と罪責 ひとつの在日朝鮮人文学論』
2014年 電子書籍kidle版『李珍宇ノート』『大藪春彦伝説』『高村薫の世界』
http://www002.upp.so-net.ne.jp/nozaki
http://atb66.blog.so-net.ne.jp/
占領期を知るための名著 Vol.35 『拝啓マッカーサー元帥様 占領下の日本人の手紙』 袖井林二郎
Published on 2017/04/05 6:05
Category: 占領期を知るための名著
Tags: 拝啓マッカーサー元帥様 占領下の日本人の手紙, 袖井林二郎, 野崎六助
占領期を知るための名著 Vol.34 『マッカーサーの二千日』 袖井林二郎
Published on 2017/03/15 10:00
Category: 占領期を知るための名著
Tags: マッカーサーの二千日, 袖井林二郎, 野崎六助
占領期を知るための名著 Vol.32 『天皇と接吻 アメリカ占領下の日本映画検閲』 平野共余子
Published on 2017/02/15 10:00
Category: 占領期を知るための名著
Tags: 天皇と接吻 アメリカ占領下の日本映画検閲, 平野共余子, 野崎六助
占領期を知るための名著 Vol.31 『本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知っていること』『沖縄・米軍基地 観光ガイド』 須田慎太郎写真 矢部宏治文 書籍情報社
Published on 2017/02/01 10:00
Category: 占領期を知るための名著
Tags: 本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知っていることー沖縄・米軍基地 観光ガイド, 矢部宏治文, 野崎六助, 須田慎太郎
占領期を知るための名著 Vol.30 坂本義和/R・E・ウォード編『日本占領の研究』 袖井林二郎編『世界史のなかの日本占領』
Published on 2017/01/15 10:00
Category: 占領期を知るための名著
占領期を知るための名著 Vol.29 思想の科学研究会編『共同研究 日本占領軍 その光と影』
Published on 2017/01/01 10:00
Category: 占領期を知るための名著
Tags: 共同研究 日本占領軍 その光と影, 思想の科学研究会編, 野崎六助