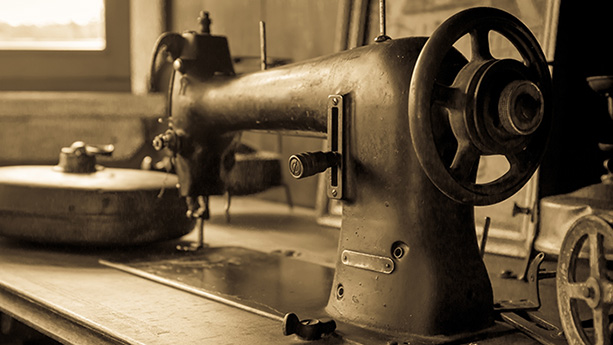今回は、「蛇の目ミシン工業 創業五十年史」の「4 機種および部品の“規格統一”」の節を見ていく。
規格統一の必要性
国産ミシンは昭和十五年(一九四〇)頃、戦前最高の年産二〇万台に達したことがある。それが戦争によって壊滅的打撃をうけ、戦後再び復興して“花形産業”を謳われるまでになったが、企業全体から見れば、まだまだ生産、流通いずれの面にも欠陥が多く、戦後にいたっても尾を引いて企業の近代化をさまたげていた。なかでも最も大きな隘路となっていたのは、機種や部品に正確な統一寸法法の取極めがなされていなかったことである。
国産ミシンには、従来からシンガーの製品規格をモデルとしてきた関係で、一応は標準規格といったものがあるにはあったが、それも組立、部品業者の技術の未熟さから、いつの間にか標準寸法に各々誤差が生じるようになった。たとえ同一部品であっても、寸法が区々なために品質のバラツキが多く、それらの部品を購入するメーカー側では、その都度手直しが必要となって、作業能率の低下や精度、耐久性などの上からも常に問題とされていた。
国産ミシンの生みの親であり、帝国ミシンの創業者である小瀬與作は、すでに当時の会社宣伝誌『スマート』(昭和十一年七月号)でこのことに触れ、“規格統一”の必要性を説いていた。
……各々の部品がその会社の製ったものでなければ規格が合わず、使用出来ないといふことでは、万一、その会社が潰れたり、或はその部品の製作を中止した場合、そのミシンは廃品同様になつて所有者に大きな損失を与へます。
一会社が自分たちの利益のために、大勢の需要者の不信を買ふといふ、この結果が良からうはずはありません。これからは世の為、人の為に業界がこぞつて共通の互換性あるミシン、或は部品をつくることが、国産ミシンの発展のため業界全般に課せられた使命であらうと信じます。(以下略)
と、業界に対して警告を与えていたのである。
“規格統一”の制定
この機種および部品の“規格統一”の問題が、戦後、ようやく業界の緊急事態にのぼることになった。
二十一年六月に帝国ミシン、日本ミシン製造、三菱電機、福助足袋、原田製作所などの肝煎りで「ミシン製造会」が発足したことはすでに述べたが、その当初、帝国ミシンを代表した前田増三によって、初めてこの問題の口火が切られた。
前田は戦前からの経験で、「ミシンの輸出には部品の“互換性”が不可欠の条件である」こと、また「国内においては近い将来、シンガーの再進出が必至である」ことに論及し、この緊急対策として、業界は大局的見地から速やかに機種、部品の規格統一を行なうことを率先提唱したのである。
こうした前田の発議が実って、同年十月には製造会の中に「ミシン技術協議会」が設けられ、その第一回会合が小金井工場で行なわれた。たまたま、この時期はシンガーの“商標権侵害”問題が起きていた矢先でもあって、業界としては、一日もはやくこの“規格統一”を急ぐ必要に迫られていたのである。協議会はまず最初に、家庭用ミシンの規格寸法の統一に着手した。全国を東部、中部、西部の三つの技術協議会に分け、各地区ごとに原案を持ち寄り、商工省の監修をうけた。二十二年十二月には標準図面ができあがり、これにもとづいた試作品が完成して、二十四年二月に部品を含めた全国統一の規格寸法を正式に制定したのである。今日の“家庭用HA-1型”の標準規格がはじめて完成された。
この標準規格の制定によって、部品の“互換性”が完全なものとなり、部品メーカーにあっては単一部品の大量生産が可能となって、製品コストを大幅に引き下げることができるようになった。シンガーですら、同一部品の生産は月三万ないし四万個にすぎなかったのに反し、後年、日本では月産五〇万個以上をつくる部品専門メーカーが輩出して、国産ミシンの発展に貢献した。このことが、のちにシンガーの巻返し、再上陸を阻んだばかりでなく、アメリカはじめ自由諸国へ進出して〈世界一のミシン生産国〉になった最も大きな要因といわれている。
シンガー商標権侵害問題と“新名称”の決定
戦後のミシン業界の大飛躍の裏には、思いがけない事件がつぎつぎと発生して関係者を悩ませた。これから述べるシンガーの“商標権侵害”問題もその一つである。
日本のミシンの生立ちが、歴史的にも当初からシンガーに範をとり、シンガーと同一同型の機種、部品の製造にあたってきたことは前述のとおりで、したがって機種の名称とか部品番号等は家庭用、工業用を問わず、ほとんど“シンガーナンバー”を使用していた。業界の慣用語として、多年染みこんでいたこのシンガー名称がGHQの干渉によってご破算になるという、業界にとって単なる衝撃だけではすまされない大問題が起きたのである。
昭和二十一年十月、当時、商工省機械局のミシン担当官であった一ノ瀬岩三(現ミシン検査協会専務理事)は、GHQに出頭を命ぜられ、“外国製品名称使用禁止”に関する一通の覚書を手交された。
「日本の国内で生産、販売されているミシンは、シンガーの商標に類似のマークやシンガーと同一の製品の呼称、部品番号を使用している。これは外国品との不当競争であるから、速やかに全面的中止の措置をとられたい」
という、内容のものであった。
これに続いて、一ノ瀬技官はGHQの特許商標課の係官から、「今後は機種の呼称、部品番号はもちろん、“S”のつくブランドでシンガーの字体“S”に類似するもの、およびアームの下部につける金属板の小判形マークの使用を禁止する」――旨の通告をうけた。
機種、部品、針、マークの類まで、シンガー名称の使用を一切禁止されたことは、まさに青天の霹靂ともいうべき出来事であった。一刻の猶予もならない業界では「ミシン製造会」が主体となり、さきに“規格統一”の目的で設置した「ミシン技術協議会」の中に「名称委員会」なる対策機関を設けて、日本独自の新名称制定をいそいだ。ことは全業界に及び、まかり間違えば業界の浮沈にかかわる一大事であった。この問題がいかに難航したかは、その後しばしばGHQ勧告が出され、二年後の二十三年八月にいたって、ようやく商工省からつぎのような正式公示が行なわれたことからもうかがえる。
外国製品名称使用禁止
GHQの覚書により、外国製ミシン、同部品、及びミシン針の名称、番号等を。
日本製品に使用する事は固く禁じられたので、昭和二十三年九月末日以降、凡て。
のものに一切之を使用しない様注意されると共に、今般日本製品に対し、使用す。
べきミシン並にミシン針の称号を左記(略)の通り決定したから、必ず之を使用。
されたい。。
なお、下記の表(略)に記載のない新製品を製造する場合は、商工省機械局に。
届出て称号の決定を受けるよう措置されたい。。
また、部品番号に就ては、決定次第通知する。。
機種及び針の新名称。
機種及び針の新名称はかねて関係団体及び関係当局で審議中であったが、この。
程正式に決定した。
戦後、国産ミシンの生産高は昭和二十一年の四万台から、二十二年は一五万台、二十三年は二〇万台と伸長をつづけていた際でもあって、このシンガーの“商標権侵害”問題は、ともすれば国際的紛糾にまで発展しかねなかったが、幸いにも商工省当局と「製造会」の斡旋尽力によって解決をみた。
この問題は、ある意味では戦後の好況に有頂天になった業界を反省させ、一種の覚醒剤になったといえないことはない。正式決定された国産ミシンの“新名称”によって、各機種、針、部品(部品番号の決定は同年十月一日)の区別はいっそう明確となり、現在では、海外においても、シンガー名称よりこの日本名称のほうがかえって普及するまでにいたったのである。
余談であるが、シンガーの日本再上陸説は、右に述べた商工省の一ノ瀬技官がGHQに出頭の際、特許商標課のトップキンス係官の傍にロートンという人物が同席していたことから噂が立った。彼は元シンガーの日本駐在の幹部社員であり、戦後はGHQの嘱託となって来日していたので、このへんにシンガーの日本に対する“巻返し”が云々された原因がある。
また二十二年の秋には、戦前、シンガーの横浜中央店代表であったオーレルが、今回はシンガー副社長の肩書で来日した。オーレル副社長は来日早々、帝国ミシン小金井工場を訪れてつぶさに工場内部を参観したのち、昭和七年のシンガー大争議の際、社員代表として会社に敵対した山本東作(当時、全日本ミシン商工業組合理事長)と面談し、つぎのような会話を交している。
「こんど貴方がシンガーの副社長として来日されたのは、どんな用向きですか」
「特命ですから、お話しするわけにはいきません」
「蛇の目ミシンの工場をご覧になったそうですが、ご感想はいかがですか」
「たいしたものです。とくに日本では労賃の安いことが羨ましい」
「シンガーではいつごろ日本へ企業進出するおつもりですか」
「いや、シンガーは日本が自由貿易にならなければ進出しません」
当時はわが国の貿易はすべてGHQの管轄下におかれて、為替管理も厳重をきわめていたが、日本通のオーレル副社長がシンガー再上陸を狙い、日本のミシン産業の実態調査を進めていたことは事実であろう。オーレルが再度来日したのは昭和二十九年であって、この年、わが国のミシン業界を文字どおり震撼させたいわゆる「S・P問題」(シンガーとパインの提携問題)がもちあがった。
「第二編 蛇の目ミシン沿革」の「第三章 受難期 帝国ミシン後期」は、いよいよ佳境に入り、次回の「5 『蛇の目ミシン株式会社』と社名変更(1949年)」で一応終了とする。つまり、続きの「第四章 再建期 蛇の目産業時代(1950年~)」と「第五章 飛躍期 蛇の目ミシン工業時代(1954年~)」は残念ながら省略する。

-
プロフィール:小川 真理生(おがわ・まりお)
略歴:1949年生まれ。
汎世書房代表。日本広報学会会員。『同時代批評』同人。
企画グループ日暮会メンバー