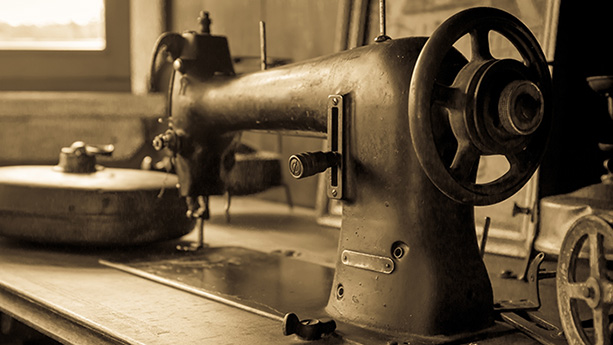今回は、「蛇の目ミシン工業 創業五十年史」の「2 終戦とミシン事情」に引き続き、「3 めまぐるしい役員交替」を見ていく。
旧役員の復帰運動
「帝国ミシン従業員組合」が二十一年一月に結成をみたことはすでに述べたが、三代目の組合委員長に丸山幸一(現本社専務)が選ばれたその年の夏頃から、社内では前田、高木、丸山、阿部らの幹部社員によって、小瀬與作以下の旧帝国ミシン経営者の復帰運動がひそかに進められていた。
この“旧役員復帰運動”の起こった動機というのは、岡田新社長、加瀬専務の経営方針が前田らの不信を買ったことにあった。岡田社長以下は目先の利益や自己の保身に汲々として、ミシン製造再開後の対策にも何一つ為すところがなかったのである。
ミシン製造再開にあたって、前田は沖系経営陣の中でも最も信頼できる松本播州取締役(前沖電気取締役製造部長)を生産責任者に推し、また販売面では速やかに国内直営網を復活して「予約・月賦販売」の再開に備えること――を幾度か進言したが、岡田、加瀬の両首脳は「親会社である沖電気の意向云々」を口実にして耳をかさなかった。
わずかに、元本社のあった日本橋江戸橋加賀ビル内に東京支店を復活させたほか、大阪と広島に出張所という名目で販売所が設けられたにすぎない。戦前、六十数店を数えた直営支店はすでに廃棄処分にされたあとで、見る影もなくなっていたのである。そればかりでない、奇怪なことには工場倉庫に貯蔵されていたミシン資材が、某重役の差し金で夜な夜ないずこかへ運び去られている、という噂まで立つようになった。
終戦を境として、旧帝国ミシン系の社員と沖系の現首脳部との間には、おのずから”ミシン“に対する認識、熱意の度合いがちがっていたのは当然としても、このような噂が真実明るみに出るにつけて、両者の感情的対立は日毎に深まっていった。そして、前田側から「沖にミシン再興の意志がない以上は、会社の経営権を帝国ミシンの創始者である元の経営者に返すのが至当である」――として、旧役員の復帰運動がしだいに表面化するにいたった。
こうした前田側の主張の裏には、“日本の産業を戦前の旧態に復す”――という、ポツダム宣言に盛られた“経済民主化運動”が大きな拠りどころとなっていた。折も折、会社が“制限会社”に指定されたさい、政府機関の持株整理委員会によって凍結されていた”株式“が条件つきで放出されることになったのである。
前田はこの自社株式を社員買受けのかたちで買いとり、これによって旧役員の復帰をはやめようとし、買取資金の調達を当時「理化学工業株式会社」(リッカーミシンの前身)の常務であった嶋田卓彌に依頼した。嶋田は小瀬退陣と同時に会社を退くにあたって、前田と戦後のミシン事業再建の盟約を交し、今回の旧役員復帰運動を蔭から見守っていた人である。ただちに理化学工業社長平木信二(現リッカーミシン会長)宮崎清(当時、三井物産社長)らと諮り、こころよく資金の援助を約諾した。
一方、日頃から前田らの言動を不穏分子と見なしていた岡田、加瀬の首脳部は、この運動を阻止するため卑劣な裏面工作を行なった。いわく、「帝国ミシンの旧経営者は、戦時中自己の所有株を沖電気に売却し、会社や従業員を見棄てて逃げだした。かような不徳義漢に今後の経営を委すことはできぬ」と逆宣伝につとめ、沖系の出向社員を利用して内部攪乱をはかった。
その挙句、こと面倒とみた沖電気側は、帝国ミシンの全株式民政党の元代議士三好英之に譲渡して、経営権を肩替りさせてしまったのである。二十一年八月に専務の加瀬矩郎が退任、つづいて九月には岡田武社長も退任した。三好英之は戦時中商工政務次官をつとめ、公職追放をうけていたので表面にこそ出なかったが、もっぱら蔭の実権者として睨みを利かした。
沖電気と気脈を通じていた三好派の、前田らに対する圧迫は一段と露骨になった。従業員組合幹部(当時の委員長清水富雄)の抱き込み、旧帝国ミシン従業員の切崩しに多額の金がばらまかれ、はじめは前田らの主張に共鳴していた者のなかからも離反するものが出てきた。あとは、過去の事情を知らない戦後新しく入社した従業員ばかりである。この懐柔策に乗ぜられて組合執行部の意のままに動かされた。
こうした形勢を見てとった首脳部は、十二月中旬にいたって、「緊急職場大会を開き、旧役員復帰の賛否を組合員の投票によって決定する」旨を一方的に通告し、職場大会は二十八日開催することに決まった。たまたま「帝国鋳造株式会社」の総会に出席のため、同社の監査役であった前田は山形へ出張中であったが、大雪に閉じこめられ、大会前日にようやく帰京することができた。その間に、会社側のお膳立てはすべてできあがっていたのである。
十二月二十八日は工場の御用納めの日である。大勢の工員たちは明日からの正月休暇や郷里へ帰省のため、うきうきとした気分になっていたその日の午後、終業間際の時間をねらって緊急職場大会が強行された。しかもその投票方法は組合幹部が各職場毎に投票用紙を持ち廻り、彼らの眼前で、賛否を記入させるという手のこんだやり方であった。
投票の結果はもはや明らかであった。前田派の敗北に終わったとはいえ、投票総数三七〇票のうち、その差がわずか三〇票だったことは、組合員のなかにも前田らに同調、支援する者が大勢いたことを裏付けていた。
翌二十二年の二月二十五日、復帰運動の首謀者と目された前田ら一三名の幹部社員は連袂退社した。前田増三、高木正一、丸山幸一、阿部久明、木村忠雄、井上準暁、高岡勇、小澤良徳、麻生勝實、小山竹二、島田三郎、金田辰治、松本清の一三名である。いずれも帝国ミシン生え抜きの同志で、この事件のあと麻生勝實だけは一時、資材課長の現職にとどまったが、他は遠ざけられ、休職を命ぜられていた。
この旧役員復帰運動のリーダーであった前田増三は、それから二十数年の歳月が経った現在、蛇の目ミシンの社長の椅子についている。思えば不思議な因縁というべきであろう。
前田は当時を回想して
「……復帰運動の背景には、日本の産業を戦前の旧態に復せというポツダム宣言
があったということは確かだが、もし当時の首脳部が、ミシン再興に、真剣に取り
組んでくれたら、われわれは協力を惜しむどころか、むろん復帰運動などは起きる
こともなかったろう。
……われわれは自分たちの信念にもとづいて行動した。仮に従組を金銭で買収し
て勝ったとしても、このため従組に乗ぜられて、経営にまで容喙されることを惧れ
たのである。
……われわれの主張と行動が正しかったことは、われわれが去った後の会社の推
移を見れば、よくわかってもらえると思う」
と、語っている。
その後の前田ら一三名の去就については、つぎの嶋田の手記(『私の履歴書』日本経済新聞社刊)が明らかにしている。退社一年の後、前田は嶋田、平木らとともに「リッカーミシン株式会社」を創立した。
決戦投票に敗れて間もなく、前田君がわたしの会社(理化学工業)に飄然と現
われ、例の屈託のない大声で、頓挫までの経過をくわしく話してくれた。
その際、蛇の目はミシンの予約・月賦販売をやらぬと公表しているから、会社
を辞めた十三名の退職金を資金にして、新しいミシン会社をつくれないだろうか
……という話も前田君から出た。
わたしの勤めていた理化学工業という会社は、そのころ雑繊維関係の新製品を
開発していたが、借金ばかり多い貧乏会社だった。しかし、わたしにはかつて蛇
の目をやめた時、前田君と“戦争が終わったらまた一緒になって、ミシン事業を
やろう”という黙契がある。
早速、わたしが産婆役になって理化工の重役会に新会社設立を諮った。その結
果、資本金は一九万五〇〇〇円で、これは理化工側と前田側全員の折半出資。別
に当座の運転資金として四〇万円を融資することが決まった。
新会社の名称は、親会社の理化学工業にちなんで「リッカーミシン株式会社」
とわたしが名付親になった。本社は神田鍛冶町一丁目、発足したのは二十三年二
月であった。社長には理化工社長の平木信二氏、副社長に小瀬與作翁を引っぱり
出して、嶋田が専務、川本日出生氏と前田増三氏が常務になり、高木、阿部氏ら
を取締役にすえた。
また、復帰運動につづいてこの新会社設立にも大変お世話になった宮崎清氏
(前三井物産社長)に会長になってもらい、非常勤役員として小宮山武嘉氏(当
時独立してクリスターミシン工業株式会社を設立)、のちに副社長に就任した安
藤喜六氏を加えて、ほとんど戦前の帝国ミシンの主だった経営者が顔を並べた。
蛇の目をやめた十三名のうち、麻生、金田両君は独立してミシン部品卸業を自
営し、松本君は千葉でミシン販売店を開業して、リッカーには入社しなかった。
春秋の筆法をかりれば、前田らの旧役員復帰運動の挫折が今日の「リッカーミシン」を生んだともいえる。世間からみれば、たんなる帝国ミシンの内輪揉めにすぎなかったが、さきの前田の言葉にあるごとく、この“内紛”を契機として帝国ミシンの社運は急速に傾いていった。事件が一応決着した昭和二十二年二月七日、すでに会社の実験をにぎっていた三好英之は、彼の身代わりとして山下農夫也を取締役社長に任命した。これで帝国ミシンは、戦後四代目の社長を迎えたことになる。
“販売権”をめぐる業界の紛争
さて、ここでは終戦直後の“ミシン国内販売”の実情について簡単に触れてみたい。
前にも述べたように、業界は平和到来とともに一陽来復、ふたたび活況をとりもどしたが、肝腎のミシン価格は、戦争中の申し子である「公定価格」によって頭を押えられたままであった。いわば販売そのものが前注文同様の配給制に近かったため、これによって利益を得るのは小売業者だけであって、製造業者は、ただ資材の入手と増産にその日その日を追われるという変則的な状態がつづいていた。
このため二、三の大手メーカー筋から公定価格を更新して、ミシン販売を本来の“自主販売”の線に戻そうとする動きが出てきたのも無理からぬことだった。しかしこうした動きは戦時中、ミシン販売を独占していた販売業者側からつよい反対をうけた。当時は販売業者の団体として、戦争末期に生まれた「全日本ミシン商工統制組合」がまだ存続しており、はからずもミシンの“販売権”をめぐって、メーカー側団体「ミシン製造会」との間に紛争がもちあがったのである。
調停にはいった商工省(昭和二十四年、通商産業省となる)では、機械局内に「ミシン需給協議会」を設けて両者間の意見調整につとめたが、問題が問題であっただけに解決が容易でなかった。あくまで戦時中の規約を楯に、製品の引渡しを要求して譲らぬ販売業者側と、戦争によって不当に歪められた“販売権”の正常化を主張するメーカー側との利害がはげしく対立した。
結局、メーカー側の主張が通り、戦前からの既成事実が認められて事件は落着した。当時、帝国ミシンの総務部長の職にあった前田増三は、メーカー側を代表して販売業者組合、商工省当局との折衝の矢面に立って活躍した。その前田が「戦後の蛇の目をおそった最初の危機」――と見ているくらい、この”販売権“の帰趨は会社の将来を左右する大問題だったのである。この紛争解決にあたって、帝国ミシン、ブラザーなど東西の主力メーカーの一致協力が与って力があったといわれている。
業績の悪化がつづく
新社長山下農夫也の就任と同時に、三好側からは菅谷脩三、三好基之が取締役として送り込まれたが、いずれも名目上の役員にすぎない。沖電気の松本播州と加藤彬がそのまま残留して、引きつづき実務を担当した。
二十二年四月、前述の業界紛争が一段落した直後、GHQの指令によって「独占禁止法」が公布された。経済民主化にのっとり、大企業の製造部門と販売部門を分離させて企業の独占支配を排除しようとしたもので、ミシン業界においても、大手メーカーはみなこの適用をうけることになった。このため、帝国ミシンでは戦後再開した東京支店を閉鎖し、独立の会社として同年九月、「蛇の目ミシン販売株式会社」(資本金五〇万円)を銀座三丁目二番地に発足させ、これに従来からの大阪、広島両出張所に加えて福岡出張所を新設して、販売会社の系列下に入れた。
新社長の山下農夫也については詳らかでないが、当時、前田らの退社直後に満州から引き揚げて会社に復帰し、山下の下で働いた廣谷豊蔵(現本社専務)によると、「山下は三好の属していた民政党の院外団出身で、三好とは親分子分の関係にあった。三好が戦時中、岸信介の下で商工参与官と商工政務次官をやり、戦犯として公職を追放されたため、その身代わりに社長となった人で、もともと経営者の器でなく、ロボット的存在――」にすぎなかった。
山下在任当時の、昭和二十二年度のミシン生産実数は上期六六二七台、下期八二九七台の数字を示した。これを見ても上昇の機運にあったが、右の廣谷の言葉のごとく、山下は事業にはまったく無縁な素人経営者であった。目先の好況を奇貨として、ずさんな経営に終始したため、毎期一〇〇万円に近い赤字が出はじめた。果ては負債が山積し、給料の遅配、諸税滞納による差押え騒ぎまで惹き起こすようになり、山下は経営悪化の責任を問われて、翌年二月、わずか一カ年の在任で社長の座を追われる破目になった。
その後五カ月にわたって、再び会社は社長空席のまま、有名無実の経営陣が猫の目のようにめまぐるしく交替した。しかも、社内は情実人事にからむ派閥抗争や従業員組合の労働攻勢に明け暮れて、その間の業績には何ひとつ見るべきものがなかったばかりか、かえって会社を破滅寸前にまで追いやってしまったのである。
しかし、このこととは別に、会社へは終戦直後から二十三年にかけて、復員した技術将校と大学機械科新卒者の新進気鋭の技術者たちの入社がつづき、小金井工場の技術陣が充実をみたことは将来への希望をつなぐ唯一の救いでもあった。このスタッフとは中村静夫常務(蛇の目精密社長、本社技術研究所長兼任)、田宮由道(現製造部長)、富田澄(現貿易部長)、田中義一(現小金井工場長)の現本社取締役をはじめ、廣瀬麟一(現ミシン検査協会専務理事)、五十嵐良忠(現製造部嘱託)、栗田邦太郎(現蛇の目精密専務)、四谷輝久(現蛇の目精器常務)、江口保賢(現蛇の目電機取締役工場長)、高樋信也(現蛇の目精密取締役工場長)、三好正男(現蛇の目金属取締役工場長)、羽生進(現本社技術研究所室長)、鈴木満喜(現小金井工場次長・嘱託)らである。
今回はここで終わり、次回は「4 機種および部品の“規格統一”」の節に移る。

-
プロフィール:小川 真理生(おがわ・まりお)
略歴:1949年生まれ。
汎世書房代表。日本広報学会会員。『同時代批評』同人。
企画グループ日暮会メンバー