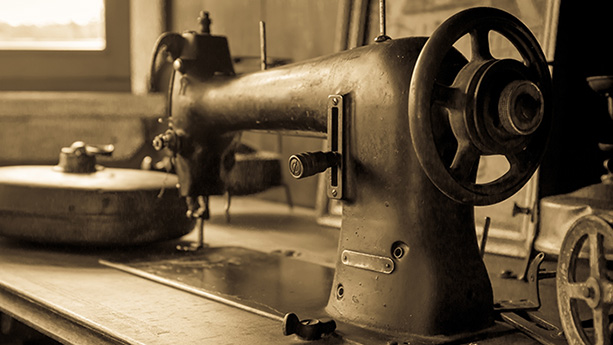かつて家でミシンを踏む母親の姿をよく目にしたものである。そこで、「蛇の目ミシン工業 創業五十年史」で、敗戦後のミシン事情について調べてみよう。
同社は、世界最大のミシン・メーカーであるが、一九二一年にパインミシン裁縫機械製作所として創業されてから、三五年に帝国ミシン株式会社、敗戦後の四九年に蛇の目ミシン株式会社、五〇年に蛇の目産業株式会社、五四年に蛇の目ミシン工業株式会社と変身を遂げてきている。
したがって、「第三章 受難期 帝国ミシン後期」を見ていく。
前略……そして、十九年七月にはミシン団体の全国一本化が進められ、メーカー側の団体である「日本ミシン製造工業組合」と販売業者側の「ミシン商業統制組合」の両団体を統合した「全日本ミシン商工統制組合」が結成された。これには帝国ミシンの前常務で、小瀬と共に退任した安藤喜六が理事長に推されて就任した。
全国統一の組織を固め、資材、製品の配給統制にのぞんだ業界であったが、すでにその頃には兵器に準じた工業用ミシンといえども原・材料の配給割当がほとんどなくなり、所期の目的を達することはできなかった。二十年八月六日、九日には原子爆弾が広島、長崎に投下されるにいたり、戦局の帰趨はもはや明らかとなった。
2 終戦とミシン事情
窮乏をきわめた国民生活
昭和二十年(一九四五)八月十五日、日本はついにポツダム宣言を受諾して無条件降伏した。
太平洋戦争の勃発以来三年八カ月、さらにさかのぼれば、十二年七月の日華事変から実に八カ年にわたった長期戦もここに終熄し、日本は有史以来はじめて“敗戦”の屈辱をあじわったのである。
戦災都市は一一九の多きにのぼった。東京、大阪はじめ名古屋、横浜、神戸その他地方都市の大半は焦土と化し、あとには焼け崩れた瓦礫と傷つき疲れきった国民だけが残された。
九月二日、ミズーリ艦上で降伏文書調印。
九月八日、マッカーサー元帥東京に進駐してGHQ(連合軍総司令部)を設置。
詩人三好達治は「今は苦しい時だ/長い激しい戰さのあとで/四方の兵はみな敗れ/家は焼け船は沈み/山林も田野も蕪(あ)れて/この窮乏の時を迎へる」と荒廃した国土を詠った。戦い敗れた国民は文字どおり虚脱状態におちいり、混乱と窮乏のどん底に喘ぎながら、つぎつぎと襲ってきた。深刻な食糧危機、悪性インフレのなかで、その日その日の生活を切り抜けてゆくのが精一杯であった。
終戦直後の六大都市では、主食の配給量は一般成人一日米二合一勺(二九九グラム)であったが、これとても遅配がちで当てにならなかった。焼跡のあちこちにできた“闇市”で雑炊や芋汁、玄米パンの類をむさぼり食うか、あるいは焼けのこった衣類や家財を抱えて農村へ買出しにでかけ、米とかサツマイモと交換してわずかに飢えを凌いだ。
住居を焼かれ、行くあてのない人々は防空壕や焼けトタンで囲ったバラックに、一枚の畳も寝具もない着のみ着のままの姿で住んでいた。
衣料は、衣料切符はあったがこれも名目だけのもので、終戦の翌年にはスフ入りサラシ三ヤールの配給が一度だけあったきりだった。国民服、兵隊服はもちろん、フロック・コートの上衣にカーキ色の兵隊ズボン、それに下駄履きというちぐはぐな恰好でも誰も不思議に感じなかった。なかにはスフ入りの毛布を、手づくりでオーバーに仕立てて着込んでいた器用な女性もいた。
ミシン需要高まる
戦時の女性の服装は、老若とも筒袖にモンペというのがもっとも実用的なスタイルであった。その後も、モンペ姿で買出しに行く風景がしばらくつづいたが、全般には終戦の翌年あたりから減りはじめ、女性の服装はいつの間にか“洋服化”していった。彼女たちは残り布や端切などの手持ち材料を利用して、思い思いに洋服らしいものをつくりあげた。それらは“更生服”と呼ばれて、服飾家の花森安治は雑誌『スタイルブック』(二十一年七月号)で大いにこれを推賞した。
生地屋さんで買つてきた服地だけが服をつくる材料ではないと考へましやう。あな
たの箪笥の中や疎開してあつた行李の中などに、きつと眠つてゐる何枚かのきもの、
それをほどけばもう立派な服地をあなたは持つてゐるのです。これは洋服地、あれは
きもの地と区別して考へることは、もともとをかしいことでした。
こうして“更生服”が街に目立ちはじめた頃、ミシンに対する需要がにわかに高まってきた。衣服の加工、更生に、家庭や縫製工場でもミシンの絶対量が不足していたのである。したがってミシンと名がつけば、火をかぶった頭部を塗り代え、部品を補充してつくり直したいわゆる“焼けミシン”でさえ引っぱり凧のありさまであった。
理由はいうまでもなく、戦時下、家庭用ミシンの製造が禁止され、工業用ミシンもまた軍需専用となって民間に長期間補給がなかったことと、戦災によって大量のミシンが焼失したことにあった。戦前の昭和十五年に、全国で一七〇万台あったミシンの半数以上を戦災で失い、終戦時には六〇万程度が焼け残っていたにすぎなかったという。
こうした需要に支えられて、ミシンの生産は急ピッチで再開された。戦前、ミシン製造に携わっていた業者は倉庫の一隅に放置した治工具や鋳型の埃をはらい、ふたたび元の本業にたち返ったが、電力の使用制限、資材難は戦時中と変わらず、そのうち食糧・住宅難の苦労が重なって、軌道に乗るまでにはまだ時間がかかった。終戦の年の国内ミシン生産高は家庭用二一五〇台、工業用二二六五台、二十一年度はやや回復したものの四万五九〇二台を生産したにすぎなかった。気狂いじみた旺盛な需要に比べて、それこそ焼石に水の状態だったのである。
ついでに他の諸工業に触れると、とくに鉄鋼、機械、繊維関係は惨憺たるありさまであった。二十年九月は昭和十一、二年を一〇〇とすると、、その生産指数は鉄鋼二・五、機械二・七、繊維四・五で、生産活動は停止されていたも同様であった。またわが国の製造工業と鉱業を含めた総合生産指数も、二十年八月には八・七まで下がって、日華事変前の十分の一以下という貧困さであった。
軍需工場からミシン産業へ転換
このように見ると、二十一年度のミシン生産高はわずか四、五万台にすぎなかったとはいえ、戦後のミシン産業の立ち直りは著しく早かったといえる。戦前のミシンメーカーの復帰はいうまでもなく、マッカーサー指令によって兵器生産を禁止された会社が続々とミシン産業へ転換したためでもある。政府の認可を得れば、中小企業の圧倒的に多いミシン産業への転換が容易であったが、なんといっても最大の理由は、当時ミシン産業が唯一の平和産業として脚光を浴び、時ならぬ“ミシンブーム”をまき起こしていたことにあった。
戦後、軍需工場からミシン製造に転換した会社は、日本製鋼宇都宮製作所(パインミシン)、中島飛行機浜松工場(リズムミシン)、津上製作所(ツガミミシン)、日立造船(ヒタチミシン)東京重機工業(ジューキミシン)、愛知工業(トヨタミシン)、その他石川島芝浦タービン、川南造船所、石井精密、大和田工業、千代田工業、東京螺子等である。
ところで、当時、ミシンはつくるそばから売れる――という、いわゆる“ミシン飢饉時代”を現出していたが、それにもかかわらず価格は戦前からの「公定価格」で押えられたままだった。一方では資材、労力不足から生産原価の高騰がはげしくなるという矛盾が表面化して、業界の再編成をのぞむ声が先発メーカーの間からつよまってきた。その頃はまだ戦時立法による「全日本ミシン商工統制組合」が存続していたが、それもほとんど有名無実化しており、かつまたGHQの指令をうけ、組合の解散が予告されていた矢先でもあった。
こうした必然的な要求から、戦後いちはやくミシン生産を再開した有力メーカーのうち、帝国ミシン(前田増三)、三菱電機(渋谷進一)、原田製作所(西山庸徳)、日本ミシン製造(安井正義、上田耕三)、福助足袋(安積嘉範)、朝日ミシン(大下国太郎)、精研舎(岸本豊)の七社が発起人となって、二十一年六月「ミシン製造会」を新しく結成した。資材の確保、公定価格の改正、四割という高率物品税の軽減――など、山積した重大問題解決に製造会が一致して取り組むことになったのである。
ひとたび「ミシン製造会」が発足すると、新規加入者があいつぎ、結成後わずか三カ月の間に会員は五〇社を突破した。最初の役員会社はつぎのとおりである。
(理事会社) ・東部 帝国ミシン 日本製鋼 津上製作所
・中部 日本ミシン製造 三菱電機 愛知工業
・西部 福助足袋 産興ミシン 朝日ミシン
(監事会社) ピースミシン 富士ミシン
(評議員会社) 東京重機 朝日奈機器 原田製作所 東京朝日ミシン 田中亀七工場
増島製針所 浜松楽器 精研舎 東洋ミシン 錦綾工業 小野製作所
興亜ミシン
なお、この「ミシン製造会」は二十三年五月に発展的解消をとげ、「日本ミシン工業会」として再出発することになった。工業会は「公定価格と物品税の撤廃」、「部品の規格統一」という難事業に取り組み、戦後のわが国ミシン産業発展の基礎づくりを見事になし遂げた。
小金井工場の生産再開
さて、小金井工場は幸いにも戦災を免れ、終戦の日から一週間後には、はやくも他社に先がけてミシン製造再開に着手することができた。これには戦時中、沖側首脳部の意向を拒んで、ひそかにミシンの製造技術と資材の温存をはかった前田増三らの蔭の力が与って大きかったといわれている。前田の下には旧帝国ミシン系のミシン製造に熟達した技術者四、五〇名が残っていたので、ミシンの製造再開はいわばお家芸にひとしいものであった。これに加えて、小瀬ら戦前の経営者が残していった約四万台分のミシン本体、部品等の資材が、工場倉庫に手つかずのまま山積していたのである。
前田は当時、本社(江戸橋の本社焼失後は小金井工場内に移した)の総務部長の職にあったが、このへんの事情についてこう語っている。
「……戦後ただちに手をつけたのは工員の身の振り方だった。工場には地方からの
少年工と女子行員、その他若干の徴用工がいたが、これらの工員たちを支障なく郷里
へ帰すことが先決問題であった。
つぎがミシン製造の再開である。敗戦のショックで茫然自失となった沖側の首脳部
を説き伏せて、一週間の工場閉鎖ののち、ただちに製造再開にかかった。幸い小金井
工場は空襲の被害もなく、旧経営者の遺産であるミシンの原材料がそのまま残ってい
たので、蛇の目子飼いの技術者たちは、水を得た魚のように喜び勇んで機械の前に
立った。
当時どこよりもはやく、蛇の目がミシン製造再開に踏みきることができたのは、
小瀬さんらが残された遺産(資材)のお蔭である」
このミシン製造再開と同時に、社名もふたたび元の「帝国ミシン株式会社」(二十年十月二日登記)に復された。当初の月はようやく五〇〇台余の生産に過ぎなかったが、二カ月後には、戦後業界としてはじめて月産一〇〇〇台ラインに達することができた。生産機種は主に家庭用一〇〇種八三型と職業用九六種およびその部分品である。
翌二十一年にはいって、生産台数は上期三五五五台(月平均五九二台)、下期六七八二台(月平均一一三〇台)と徐々に上昇し、全国ミシン総生産高の三〇%を占めるにいたった。また同年九月には、甲府市に疎開中の旧蒲田工場を北多摩郡貫井町(現在の小金井市)に移して、工業用ミシン(主として八一種オーバーロック)の製造を開始した。十九年に買収した大阪の「富士精工株式会社」も、小金井工場から工業用ミシン部品の供給をうけて再開された。
一方、営業関係も戦地からの復員者を加えてしだいに充実していったが、まだこの時点では国内に販売店を開くまでには至らなかった。というのも、現況は“ミシン飢饉”のひときわはげしいときで、小金井工場の門前には早朝から客が市をなし、なかにはリュックサックを背負って地方からはるばる上京してきた業者が二台、三台とミシンを奪い合うすさまじい光景も見られた。“つくるそばから売れる”のではなくて、“つくる前から売れている”――代金を前納して、やっとの思いで一台のミシンを手に入れるという時代だったのである。先に触れたように、当時はまだ統制経済の制約をうけ、ミシンは「公定価格」で売買されていた。例をあげると、一〇〇種足踏式三個引出しテーブル付の現金価格が一級品で二七三〇円、二級品で二五九〇円(いずれも製造業者販売価格)であって、闇値はその二、三倍もの価格で取引がなされたという。
このように、新生「帝国ミシン」は生産、販売面とも順調なスタートを切ったが、しかし「公定価格」の枠の中の売上げだけでは、四〇〇名近い従業員の生活を支えるのに精一杯であった。企業利潤などは思うに及ばず、経営は二十年、二十一年とも終始赤字で苦しんだ。
人事面では、二十年十一月に社長の小澤仙吉が退き、代わって岡田武(沖電気取締役経理部長)が就任した。終戦と前後して、最高責任者である社長の椅子が短期間のうちに押田三郎―小澤仙吉―岡田武と交替した。加瀬専務は依然現職にとどまったが、これから以後の帝国ミシン経営陣はGHQの“経営民主化政策”の大波をかぶって、めまぐるしく交替を重ねることになる。
帝国ミシン従業員組合の結成
昭和二十一年十月十一日、敗戦処理内閣といわれた東久邇宮内閣に代わった幣原内閣に対し、連合軍最高司令官マッカーサー元帥は「憲法の改正」を命じ、併せて「日本女性の解放と選挙権付与」「労働組合の結成奨励」「学校教育の民主化」「秘密検察制度の廃止」「経済機構の民主化」――いわゆる“五大改革”の実施を指令した。つづいて「治安維持法の撤廃」「軍国主義者の追放」「財閥解体」「農地解放」等が矢つぎばやに発令され日本の支配層、各界を震撼させた。
民主化政策の一環である「労働組合の結成奨励」の風潮に乗って、国内では各地に労働組合の結成が見られ、これが二十一年五月の食糧メーデーなどの大衆運動と結びつき、労働攻勢は日に日に激烈をきわめるにいたった。二十年来の労働組合数五〇八が、翌年六月末に一万二六〇六組合と膨れ上がり、組合員数も三〇万から一挙に三六八万人に増大した。
こうした社会情勢を反映して、二十一年一月には、帝国ミシンにおいても本社・工場を含めた「帝国ミシン従業員組合」が結成され、その委員長に前田増三を選任した。すでに繰り返し述べたように、前田は戦前から旧帝国ミシン従業員の衆望を担い、社内外に影響力が大きかった。戦後の混迷時代を乗りきる最適任者として、初代委員長に推されたのである。
「帝国ミシン従業員組合」は組合員三七〇名をもって構成され、前田の統率の下に健全な組合活動を目的に第一歩を踏みだした。従業員の待遇問題、労働条件の改善、団体交渉権の確立など委員長として前田のなすべき仕事は多かったが、つねづね「労組は不当に強大な力をもつべきではなく、経営にも容喙すべからず」とした前田の節度ある指導方針は、労使共に好感をもって迎えられた。
労資協調の実を挙げ、会社再建のメドが立ったのを見届けた前田は、二カ月余りではやばやと委員長の座をおりた。以後の委員長は清水富雄―丸山幸一―高野光格―清水富雄(再任)とひんぱんに入れ替わったが、この交替はのちに述べる前田、高木、丸山らによる“旧役員復帰運動”がからんだためである。
財閥解体と帝国ミシン
終戦から一年経った二十一年八月十五日、帝国ミシンは「会社経理応急措置法」によって“特別経理会社”に指定された。さらに同年十一月二十二日には“制限会社”に指定され、GHQの対日占領政策の重要な一環となった“財閥解体”がいよいよ帝国ミシンの上にまで及んできた。
この“財閥解体”は戦時中、わが国の産業・金融界を支配して、軍事的侵略の先鋒とみなされた旧財閥――三井、三菱、安田、住友等の一五財閥を解体し、日本が再び戦争を起こさぬよう、経済的基盤を破壊して経済機構の民主化をはかろうとしたものである。
これによって、“特別経理会社”は企業の経理面から民主的再編成を行なうことを強制され、約八〇〇〇社にのぼった指定会社は戦時補償をすべて打ち切られてしまった。またこの年の十一月四日には、GHQの「資産凍結令」によって「制限会社令」が発令され、一五財閥その他主要会社の“解散”およびその所有する“各種財産の処分”がきびしい制限をうけるにいたった。
その後、これらの問題は、日本政府の手で処理されることになり、翌二十一年八月に「持株会社整理委員会」が発足して解体の担当機関となった。同委員会は五次にわたって指定した持株会社八三社に対し、持株会社の所有する有価証券を委員会に移譲させ、資本の変更、利益配当、動産不動産の売却を禁止した。つづいて、同年十一月には「証券保有制限令」にもとづき、財閥関係会社として制限会社四七八社が指定をうけた。
帝国ミシンはこの制限令に抵触して、“制限会社”に指定されることになったが、これにはつぎのような理由があった。
昭和十八年七月、会社の経営が沖電気に移ってから、帝国ミシンの株式は沖電気の子会社である「沖電気証券株式会社」が保有(全株の約六〇%)するようになった。沖電気、沖電気証券とも安田財閥系の会社であったため、帝国ミシンもまた安田関係会社と見なされたのである。事実この沖電気、沖電気証券は同年十二月の第二次持株会社に指定されており、このため沖電気証券所有の帝国ミシン株式は、持株会社整理委員会によって凍結されていた。
整理委員会がこれらの持株会社や制限会社から取得した株式は、当時、払込み総額で二〇〇億円を超えるといわれたが、これを二十一年九月から“国民間に民主的に再配分し、特定人に多額の株式が再集中しないようにする”――との条件つきで、逐次、株式の放出処分が行なわれることになった。
以上で、「2 終戦とミシン事情」の項は終わる。3項目以降は次回に回そう。

-
プロフィール:小川 真理生(おがわ・まりお)
略歴:1949年生まれ。
汎世書房代表。日本広報学会会員。『同時代批評』同人。
企画グループ日暮会メンバー